語り手がまさかの“アレ”!?
朝井リョウ『生殖記』を読了しました。
正直なところ、最初にあらすじを読んだときは「えっ!?」と声が出ました。なんとこの物語、語り手が“生殖本能=男性器”なんです。
この突飛な設定に驚きつつも、読み進めるうちに、そこには鋭く、優しく、そして深く人間を見つめる視点が隠されていました。
あらすじと基本情報
主人公は、家電メーカーの総務部に勤務する33歳の男性・達家尚成(たつや・しょうせい)。
同性愛者である尚成は、これまで「普通の会社員」として周囲に擬態しながら生きてきました。
恋愛や結婚、出産という「当たり前」のライフコースから距離を取りつつも、彼はいつも周囲の視線や無意識の圧力を感じながら生きています。
そんな彼を30年以上見つめ続けてきたのが、語り手である“私”。彼の「生殖本能(=男性器)」です。
存在しているのに出番がなく、社会のレールから外れてしまった尚成とともに、自分の居場所を模索し続けています。
書誌情報:
タイトル:生殖記
著者:朝井リョウ
出版社:小学館
発売日:2024年10月
価格:1,870円(税込)
ISBN:9784093867306
“生むこと”を前提とした社会の違和感
この小説で描かれているのは、まさに「繁殖=発展=正義」とされる価値観に対する問いかけです。
結婚して、子どもを持ち、家を買い、社会の一部を構成する。それが「当然」とされる社会の中で、自分はどこに位置しているのか。
語り手である“生殖本能”は、そんな社会に対してユーモラスに、でもどこか切実にツッコミを入れていきます。
尚成は、特に誰にも迷惑をかけず、淡々と生活をしています。けれど、その日常には、誰にも見えない“孤独”と“疎外感”が潜んでいるのです。
笑ってしまうのに、刺さる
語り手の語り口はとにかく軽妙でテンポがよく、何度もクスッと笑ってしまう場面がありました。
ですが、ふとした瞬間にその裏にある“切なさ”や“怒り”がにじみ出てきて、読者の胸を打ちます。
とくに印象的だったのが、語り手が「皆、何かしらのごっこ遊びを続けているだけなんじゃないか」と思う場面。
「本当は皆降りたいんじゃないのかな(中略)”今よりももっと”を常に続けていかないといずれ立ちいかなくなるこの世界の仕組みから」
この問いは、LGBTQの人々に限らず、子どもを持たない選択をした人や、社会の期待から距離を取って生きている多くの人に響くのではないでしょうか。
「成長」や「前進」が前提ではない人生もある
この小説では、“変わらないままでいること”や“社会の理想とされる方向へ進まない選択”を、否定しません。
むしろそこにある静かな尊厳を、丁寧に描き出しています。
私たちはつい、「前に進まなければ」「成長しなければ」と自分を追い込みがちです。でも、『生殖記』はそんな焦燥をふっと和らげてくれる作品でもあります。
読後の余韻と、自分への問い
読み終わった後、私が最も印象に残ったのは、「自分の人生に、本当に“正解”があるのだろうか?」という問いです。
誰かに合わせるでもなく、誰かを否定するでもなく、「こう生きたい」という小さな声に耳を澄ますことの大切さ。
それを、まさか“生殖本能”という語り手から学ぶことになるとは思ってもいませんでした。
まとめ|これは“問題作”ではなく“今”を描いた作品
『生殖記』は奇抜な設定の陰に、現代社会の問題や個人の心の機微が繊細に描かれた作品です。
笑って、泣けて、考えさせられる。朝井リョウさんの真骨頂を堪能できる一冊でした。
「なんとなく生きづらい」と感じている方にこそ読んでほしい、と心から思います。
――あなたは、自分の“出番”を感じていますか?
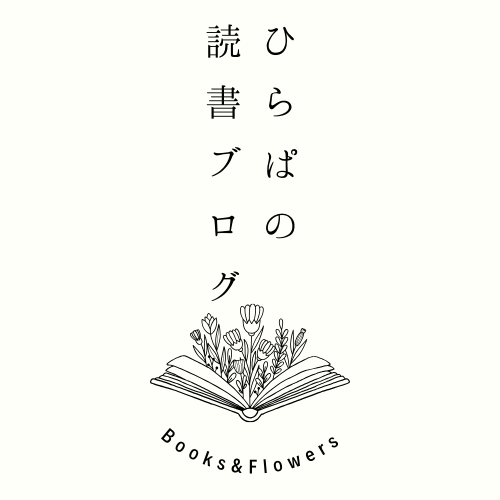
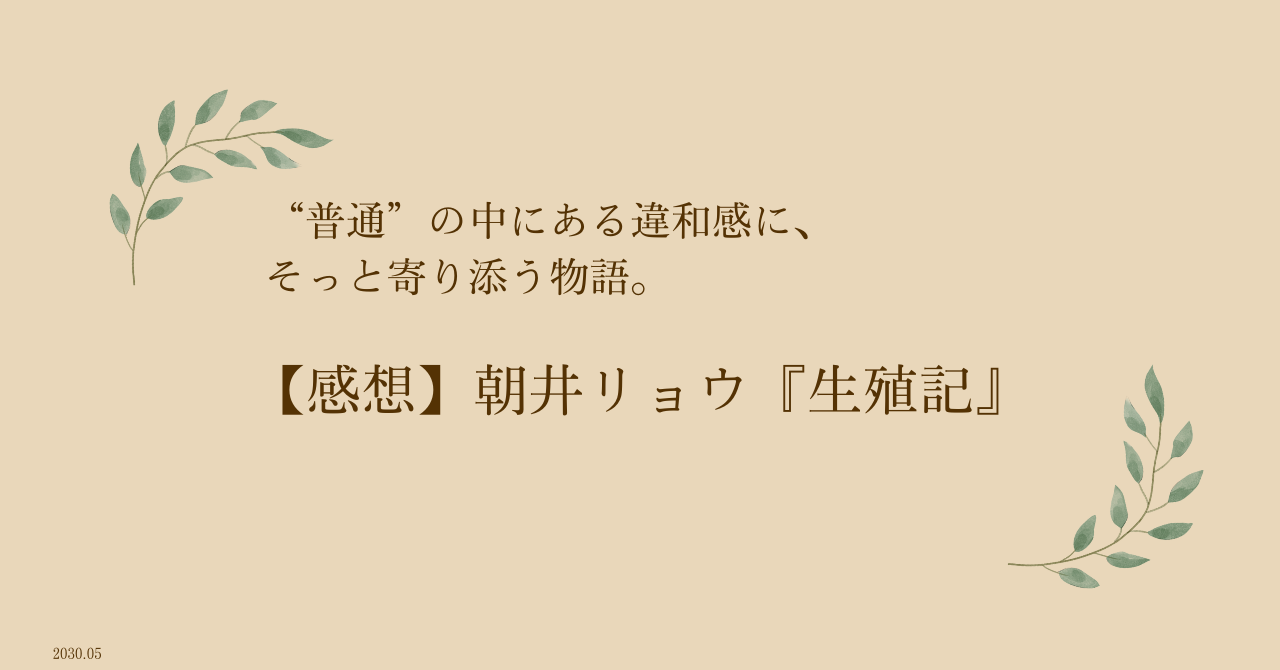
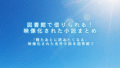

コメント