調べる力が身につく、知的好奇心を刺激する読書体験
調べ物が苦手……と感じていませんか?
レポートやプレゼン、あるいは日常生活でも「知りたい情報にうまくたどり着けない」という声をよく耳にします。
そんなときに役立つのが、検索や調査の“基本”を教えてくれる本たち。
今回は、大学図書館で日々調査相談を受けている私、司書の立場から「調べる力」を鍛えたい方におすすめの本を5冊ご紹介します。
1. 『レポート・論文の書き方入門』
著者:石黒圭(講談社現代新書)
📌 「調べて、書く」の一連の流れを知りたい人に
学生にとって、レポートや論文は避けて通れない壁。
本書では、テーマの選び方から調べ方、文章構成の考え方まで、丁寧に解説されています。
特に参考文献の扱い方や「信頼できる情報」の見極め方は、情報があふれる現代において大切なリテラシー。
✔司書の視点:図書館の蔵書検索(OPAC)を活用する方法にも触れており、学内図書館の利用促進にもつながる1冊です。
2. 『情報リテラシー入門』
著者:松原望(丸善出版)
📌 インターネット情報を鵜呑みにしないために
ネットで得た情報が本当に正しいか?
その判断力を育てる「情報の読み方・選び方」をわかりやすく解説した本です。
統計、グラフ、ニュース、SNSなど、日常的に接する情報の中で「何を信じていいか迷う」現代人にぴったり。
✔司書の視点:大学図書館では「情報リテラシー教育」も重要な役割。学外の情報とどう向き合うかを考える入口になります。
3. 『調べる技術・書く技術』
著者:野村進(講談社現代新書)
📌 ノンフィクション作家が教える“取材と調査”の本質
雑誌記者として活躍する著者が、取材の仕方や裏付け調査のコツを実体験から語ります。
公的資料の探し方や人に話を聞くときのマナー、調査対象へのリスペクトの持ち方など、レポートにも使える知識が詰まっています。
✔司書の視点:文献だけでなく、人や現地から得られる「一次情報」の大切さが伝わる点が印象的。情報の出どころを気にする姿勢が育ちます。
4. 『知的生産の技術』
著者:梅棹忠夫(岩波新書)
📌 調べる→考える→表現する、という知のサイクル
少し古い本ではありますが、「自分の頭で考え、アウトプットする」という知的活動の本質をシンプルに教えてくれる名著。
調査ノートの取り方や、情報を自分の中で“整理する”工夫が多く紹介されており、情報過多な今だからこそ読みたい1冊です。
✔司書の視点:図書館で集めた情報を「どう活用するか」を考えるきっかけに。読書記録をつける習慣もこの本から学べます。
5. 『大学1年生のための図書館活用術』
著者:松原洋子・矢野桂司(ミネルヴァ書房)
📌 図書館ってこんなに使えるんだ!がわかる
司書として働く私が、学生にまず手に取ってほしいと願うのがこの本。
OPAC検索、レファレンスサービス、電子資料の探し方まで「図書館を活用した調査」の方法が詰まっており、入門書として最適です。
✔司書の視点:図書館の“静かな相談窓口”である司書が、どんなふうに調べ物を手伝えるかを伝えるのにもぴったりです。
【まとめ】調べる力は、一生モノのスキル
検索エンジンの時代だからこそ、「調べる力」「情報を選ぶ力」が問われています。
図書館司書として働く中で、「どう探せばよいかがわからない」という声に数多く出会ってきました。
でも、探すための“地図”さえあれば、知識の海を自由に泳ぐことができるのです。
この記事で紹介した5冊は、いずれも図書館で借りられる可能性の高い本です。
気になったら、ぜひ身近な図書館の蔵書検索をしてみてください。
本を通して「調べる楽しさ」に出会える人が、一人でも増えたら嬉しいです📚
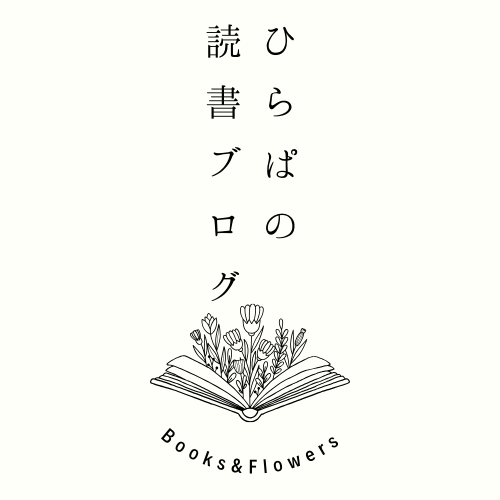



コメント